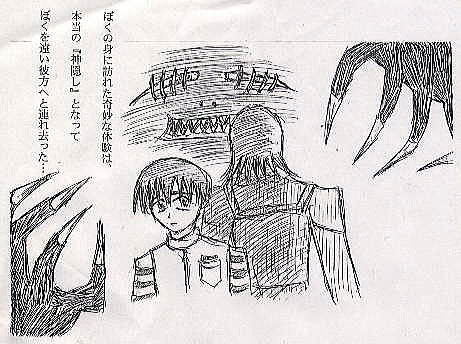
カミカクシ後編
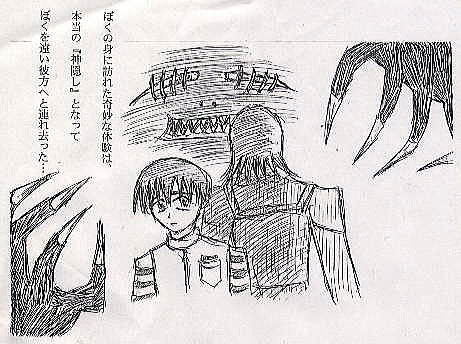
かわいそうな位に前面がひしゃげた車が電柱にめり込んでいる。車は黒煙を吹きながら嫌な臭いを撒き散らす。機械油が漏れだしている臭い。紛れもない事故現場だ。少し離れた所にぼくの父、間浩一が尻餅をついている。
「(父さんは無事か、よかった…)」
よかった?
ぼくは父さんが無事だった事に安堵した自分にふと気付いた。あの時は何も考えていなかったけど…。
「良人!」
未だ立ち上がっていないぼくに父さんは駆け寄った。
「お前は、何て危ない事をするんだ!」
「えっ?」
父さんの発言はぼくが予想だにしないものだった。気がつけば、彼の手はぼくの肩をガッシリとつかんでおり、表情も今まで見た事もない真剣な剣幕だった。
「怪我でもしたらどうする気だったんだ!」
「(父さんに…初めて怒られた…)」
初めて見る表情だ。あの年中さえない表情で、自己主張どころか感情表現のエネルギーすら見せないあの父さんが、ぼくを前にして怒っている。ふと、父さんはぼくの手足を見やった。
「…転んだ時、すりむいたのか。けがしてるじゃないか」
「あっ…」
改めて気付いた。全力で走った勢いのせいか、地面を転げた時に手足をすりむいて血が出ている。
「早く手当てするんだ、学校は遠くないな?保健室で手当してもらうんだ」
「うん、今から行くよ。父さんは仕事の途中なんでしょ?一人で行けるから大丈夫だよ…」
ぼくは立ち上がっておもむろに駆けだした。なぜか動きは足早で、この場から逃げ去ろうとしている様だった。
「痛っ!」
ぼくは右足のヒザに走った痛みで動きを止めた。
「ほろ、言わんこっちゃない!父さんもついていくよ」
「いいよ!仕事があるんでしょ!何とか行けるよ」
「それがどうしたんだ。会社には連絡を入れておく」
「でも…」
「いいから!」
ぼくは父さんの剣幕に押され、学校まで同行する事になった。道中が少し思いやられた。
ぼくと父さんは一緒に歩いていた。父さんは何も聞かなかった。ぼくも特に話せる様な話題はなく、ただ何事もなく歩いていた。思えば、父さんと一緒に歩くのは久しぶりだった。いや、初めてかも知れない。横目で見た父さんの姿は、家で見るのとは違ってぼくよりもずっと大きく見えた。
ぼくは保健室で手当てをしてもらって、校舎から出ようとした。昇降口では遅れてやって来たのか、警察の人達が父さんに事情聴取をしている。
「へえ、あれが良人の父さんかぁ」
「あっ!」
いつの間にか後ろにいたのはクラスの同級生だった。
「良人、どうしたんだよいきなり駆けだして出てってよ」
「あの真面目な良人くんが掃除をさぼるなんて」
いつの間にか、何人も集まっている。
「ゲリにでもなったのか?はっはっはっ!」
つられて他の人達も笑い始めた。ぼくに笑いが集中する。
「〜〜〜〜〜〜〜っ」
ぼくは事情を説明する事もできず、赤面しながら無言でランドセルを教室から取り、振り切る様に無言で歩いた。ぼくがこんなに目立ってしまうなんて…ぼくは気恥ずかしさで顔から火が出そうだった。
事情聴取が長引いてしまったせいか、帰る頃にはもう日が暮れ始めてしまった。相変わらず父さんとは会話らしい会話はなかったが、妙な安堵感があった。そうしてぼく達は家に帰った。
離れた事故現場の事だった。警官が話し合っている。
「やっぱりおかしいぞ…運転手はどこに消えたんだ?」
「証言によれば人は乗っていたが、降りてきた所は見ていないとの事ですが」
「それじゃあ、この事故とシートに残った血痕はどう説明をつけるんだ!」
「また…この事件か!」
警官達の苛立ちの声が夕暮れに響いた。
ぼくは縮こまる思いで母さんの前に立っていた。
「夕食買ってきてないの?」
ぼくの母さん、間志乃はぼくの顔をのぞき込む様に話しかけてくる。事故があったせいで、すっかり忘れていた。
「ご、ごめん。今から買ってくるよ」
ぼくは慌てて出かけようとした。
「待ちなさい!」
ぼくは矢で刺された様にその場に硬直した。怒られる?ふと振り返ると、母さんは冷蔵庫の中をくまなくのぞき見ていた。
「しょうがないから、今ある分ですますしかないか」
「えっ、冷蔵庫には何もないよ?」
「何もないなんて事はないわよ。とりあえずはあるわ」
「え…?」
「今日は私が何とか用意するわよ…」
母さんは冷蔵庫から余り物の野菜や卵などを取り出した。
キッチンからトントンと野菜を切る音が聞こえる。コンロから料理を炒める音がする。あの怠け者の母さんがキッチンに立っている。ぼくはリビングで新聞を読む父さんと一緒にソファーに座り、その光景を眺めていた。ぼくはその光景に美術品を鑑賞するかの様に、飽きずに見つめていた。
それから数十分後。テーブルについたぼくと父さんの前に、湯気をのぼらせる皿が運ばれてきた。簡単な野菜炒めの様だった。冷蔵庫の中に余っていた肉や野菜の残りでこしらえたものだろうか。香ばしい油の匂いが食欲をそそる。ふと見やると、エプロンを着用した母さんがそこにいた。
「どうしたの?良人」
「あっ、いや…あの程度の食材でもこんなまともな料理ができるんだなっ…て…」
「…?」
ぼくは妙に慌ててしまった。そんなぼくを、母さんが不思議そうに見ている。ぼくは何とも言えず恥ずかしい気分になってしまった。そして、缶詰などを利用した簡易なサラダや、あり合わせの食材で用意した味噌汁などを運んでくると、母さんもテーブルについた。親子三人が食卓についている。我が家では考えられなかった光景だ。
「いただきます」
不思議な事に、ぼく達の声は一堂に部屋に響き渡った。
右を見れば母さんがいる。左を見れば父さんがいる。ぼくには、家族揃って食事をした記憶がほとんどなかった。果たして、何年ぶりなのだろうか。
「良人、ご飯が冷めちゃうぞ」
横からの父さんの声でぼくは我に返った。慌てて目の前の野菜炒めに箸を付ける。
「(母さんの、手料理…)」
目の前につまみ上げたそれを見つめると、口の中に放り込んだ。程良い加減の塩と油がぼくの舌を刺激した。
「おいしい…!」
ぼくは思わず声を上げていた。
「余り物だけど、おいしいでしょ?」
「うん、とてもおいしいよ…!」
ぼくは母さんに向かってうなずいていた。黙々と箸を進める父さんも、妙に横顔が微笑んでいる様に見えた。ぼくは知らずの内におかわりをしていた。母さんは自然にぼくの茶碗を受け取り、ご飯をよそう。ぼくはその後ろ姿を見つめていた。
ぼくは、何て単純なんだ。今まで家事を押しつけていた母さんを、自己主張もできない冴えない父さんをさげすんでいたはずなのに。憎んでいたはずなのに。こんな当たり前の光景一つで何もかも許せる気持ちになってしまうなんて。自分の単純さに呆れて、何も言えない。
「ごちそうさま」
いつの間にか空になった夕食を前に、ぼくはつぶやいた。
今までお約束の様にただ言っていただけの言葉が、今は心から言える。慌ててキッチンから去ったぼくの瞳には、涙がにじんでいたのかも知れない…。
ぼくは、満腹になったお腹をさすりながら、自分の部屋へと上がっていく。部屋の中に入ったその瞬間だった。
「!?」
一瞬、目の前が真っ暗になり、世界が歪んだ。しかし、直後何もなかった様に元に戻った。
「今のは、空間の歪みか…何でまた…」
ぼくは目をこすった。また次元の狭間に飛ばされてしまうのかと思ったが何でもなかった様だ。今までと違う事に違和感を感じたが、それも忘れてぼくはしばらくすると眠りについた。電気の消えた部屋の中は、冷ややかな静寂だけがあった。
この世ではない世界、次元の狭間。この世界ではない別の世界。間良人はほんの数日前からこの世界へと迷い込む様になった。彼が聞いた話、普通の人間がこの世界へと迷い込む事はないと言う。この世に存在する人間全てが『座標』と呼ばれるものを持っているからだという。
人間、いや人間のみならずこの世の全ての存在を自分達の世界へと固定しているもの。自分達が自分達の世界に存在しているという証明。それがある限り、この世にあり得ない空間である『次元の狭間』へと立ち入る事はない。あたかもそれは、空に浮かぶ凧が空の彼方へと飛ばされない様に大地に繋ぎ止める、糸の様なものだった。
そこでふと考える。糸の切れた凧は、一体どうなるのだろうか。風に流され、何もない大空へと投げ出されるだけである。
本来あるべき自分達の世界から切り離され、『次元の狭間』へと迷い込んでしまう。
それが、『神隠し』であった。
…ぼくはふと、思い出した。
幼い頃、うっかり手放してしまった風船を。
どこまで飛んでいくんだろうとずっと眺めていた。
どんなに手を伸ばしても、どんなに追いかけても
もう手の届かないそれを。
それにしても、ここは真っ暗だな。
ここは何だろう?夢の世界だろうか。
なら喜ぶべき事じゃあないか。
夢にうなされずにすむのは。
だが、何か視線を感じる。
暗闇の中に、光る眼光の様な二つの点が…
「!」
ぼくは目覚めた。不思議な夢だった。何かがぼくを見ていた。何をする訳でもなく、まさに「観察している」と呼ぶのが正しいか。だがぼくは不思議と嫌な感じはしなかった。おもむろにベッドから下りる。
「?」
視界が歪んだ様な気がした。まだ少し寝ぼけているんだろうか。ぼくは顔を洗って朝の身支度をすませると、学校へと出発した。
学校に着き、教室に入ると男子も女子もぼくを見てクスクスと笑っている。もしかしてとは思うけどまだ昨日の話が続いているのだろうか。
「よっ、放課後ランナーくん!」
「ほっ、放課後ランナー…」
ぼくは突然浴びせかけられた変なあだ名に思わず脱力した。そして次々と人が集まってくる。
「運動会も終わったってのに何やってんだよ!」
「良人くんあの事故現場にいたんだって?」
「なかなかいい足してたな、うちの部に来ないか?」
ワイワイと次から次へと面白半分で言葉がひっきりなしに来る。何でみんなはこんな下らない事に興味を示すんだ?ぼくは頭が痛くなってきた。
「皆さん、始業のチャイムは鳴ってますよ!」
「やっべ!先生だ!」
担任の先生が来ると同時に大慌てでみんなが席につく。普通に朝のホームルームが始まった。ようやく、解放されたか。先生の話が始まり、やがて終わりを迎える。
「それから間くん、掃除は最後まできっちりやる様に!」
途端にぼくに向けてクラス中の笑い声が集中する。みんな楽しそうな顔でぼくを見ている。またか!
恥ずかしい!恥ずかしくて穴があったら入りたい気分だ。ぼくはしばらく自分に変なあだ名がつく事を覚悟しなくはならない様だ。だが、不思議とそれほど嫌な気分はしなかった。笑いものにはなったが、悪意を持って馬鹿にされている訳ではない。そのせいだろうか…。
後は何事もなく授業を終えた。ぼくは振り切る様に足早に教室を出る。また笑われるのはごめんだ。
「おっ、また走るのか?」
そんな他愛もないからかいの言葉を尻目に学校を出ていく。しばらく歩いて一人になったその瞬間だったろうか。
昨夜、朝と同じ様に視界がぶれる。世界が揺れる。
「何なんだこれは…」
次元の狭間にのまれる訳でもなく、空間が突然揺れて、すぐ元に戻る。
「何かに…見られている様な気がする…」
急に後ろが気になる。建物の影。木の影。果ては地面の小石の影。影の中に何かが潜んでいる様な錯覚にとらわれた。ただ、家に帰るというだけだというのに…。ぼくは振り返り家へと歩みを進めた。
世界が歪んでいる。見渡す限り灰色で果ても見えない。何も存在しない、虚空の広がる無の世界。この世と壁一枚を隔てた程度の近い世界。されどその世界はこの世から限りなく遠く、人間から最もかけ離れた世界。
それが『次元の狭間』なのだ。
この領域に人間が立ち入る事は例外を除いてあり得ない。人間と言わず、あらゆる生き物の存在を拒絶していると言えるだろう。だが、それとは逆にここでのみその存在を許されたかの様に生息するものが存在する。この世には存在し得ない容貌の異形の生物。彼らは『次元の魔物』といった。
この次元の狭間に一人たたずむ生き物が存在した。黒くやせ細った四肢で座り込み、小さな二つの目で虚空を眺める。彼はメネシスと名乗る次元の魔物だった。
『リョウト、何も終わっちゃいない…』
彼は、かつて会った人間の子供の名をふとつぶやく。
『お前は、逃げられない…』
メネシスのつぶやく先には、ただ何もない空間が無限と思えるほどに広がっているだけだった。
良人は家に帰宅した。今日はいつも家の中に入る事への憂鬱感はない。ふと思い直す。なぜ、家に帰る事をあれほどの苦痛に感じていたのだろうか。冷たくそびえる壁の様に思っていた家の玄関が、初めて自分を迎え入れようとしている扉の様に感じた。良人が扉に手をかけると、すんなりと扉は開いていく。
「あら良人、おかえり」
「あ…ただいま、母さん」
リビングには彼の母、志乃がいた。帰宅の挨拶を向こうから先にされたため、良人は面食らった。しばらくした後、良人は少し狼狽しながらも意を決した様に言った。
「あ、あの…母さん。できれば、今日、料理の仕方、教えてくれないかな…母さんの得意な料理…せっかくだから、ぼくにもできるやつを…」
良人は妙に落ち着かない自分に焦った。
「い、嫌ならいいんだ…母さんも、疲れてるだろうし…」
良人は慌てながらごまかす様に後に取って付けた。志乃はそんな良人を前にして一息ついて口を開いた。
「いいわよ。それ位」
「えっ…いいのかい!」
良人は思いがけず大きな声を上げていた。
「良人が料理できる様になれば楽だしね。まあ、お弁当や惣菜を買えば安上がりで手軽なんだけど…」
言い終わらない内に良人は部屋へと駆けだした。
「じゃあ、買い物に行ってくるから…!」
部屋に戻りランドセルを置くと、財布を持って外へと向かう。妙に良人の気分は高ぶっていた。
「ちょっと良人!」
「行って来ます!」
真っ直ぐに家を出た良人の顔はほころんでいた。
「(何だ…こんなに簡単な事だったんだ…何で、今の今まであきらめていたんだろう…!)」
なぜか気持ちが落ち着かない。良人は思わず笑ったまま走り出してしまいそうだった。
「!?」
家を出て一人になった、その瞬間だった。目の前の空間が歪んだ。今度は緩やかにうねり、前の時よりも時間が長かった。そして、いつもの様に元に戻った。
「一体、何なんだよ…」
良人は忌々しげにつぶやいた。直後、彼は気を取り直して小走りで駆けていった。日も落ち始め、空が夕暮れに染まる道端の影の中に、奇妙な二つの光があった。その光は去っていく良人を見つめていた。
買い物を済ませた良人は、店を出る前にトイレへと立ち寄っていた。手を洗っていた良人はおもむろに鏡を見た。その時、良人の鼓動が一瞬大きく鳴り響いた。
「!?」
良人は後ろを振り向いた。しかし背後には何もなかった。直後、視界が歪む。また、空間が歪んでいる。
「くそっ、また…!」
良人は日ごとに頻繁になる空間の歪みに苛立ちを隠せなかった。この所、一人になるといつもこうだった。
「………?」
目前の洗面台の鏡を見てみると、何かが映っている。白い二つの光。これは、良人を観察するかの様に見つめていた視線だった。良人はハッと我に返る。
「メネシス!」
鏡に映ったその姿は、かつて顔を合わせ、ある時は獰猛な次元の魔物に縄張りに入ってしまった時に自分を助けてくれたメネシスの姿だった。メネシスは口から長い舌を蛙の様に伸ばし、良人の体を捕らえると、強い力で有無を言わせず次元の狭間へと引きずり込んだ。
「(メネシス、なぜ君が…!?)」
その瞬間、空間の歪みは大きく揺らぎ、良人の体を飲み込んだ。良人は再び次元の狭間へと誘われた。濁流に呑まれる様な無力感を感じた良人は、メネシスに次元の狭間に引き込まれた事の動揺とともに、このまま二度と戻って来れない様な不安感が頭をよぎっていた。
良人の体はメネシスの舌によって宙に投げ出され、乱暴に地面とも言えない地面に放り出された。その様子は、さながら海から釣り上げられて大地に打ち上げられた魚であろうか。皮肉にも、この状況にぴったりとマッチしている。釣り人に当たるメネシスが、ゆっくりと魚に当たる良人へと近寄る。
「やっぱり君だったのか」
良人は諦めとも取れる投げやりな声でメネシスに語る。
『ああ、そうさ』
ネメシスは躊躇なくはっきりと言い切る。良人は仰向けになったまま、その声を聞いていた。不意にヌッと自分の目の前に、異形の生物の顔がのぞき込む。
「なぜ、ぼくをここへ?」
『気付いていたんだろ?お前を見つめる視線に』
「ああ、意図的に無視しようとしてただけなのかもしれない」
ぼくは目を閉じて、諦め気味につぶやいた。
「頻繁にぼくに起こる空間の歪みにもね…」
『そうか』
メネシスは溜息とともに返した。
「ぼくは、この世界から消える…」
『…まずは起きろ、話はそれからだ』
メネシスは大した感情を込める訳でもなく言った。
体を起こしたぼくは、メネシスと向かい合っていた。彼と向かい合うのはこれで四度目になるか。
『お前の『座標』がいよいよ本格的に狂い始めてきた』
ぼくは静かにその言葉を聞いていた。
『前にも言ったな…お前が自分の世界にいるためにある『座標』は常人と違い狂っている。だからお前はここ、
『次元の狭間』に迷い込む』
「君はその事を『居場所がない』って言ったよね。その通りだったんだ、ぼくは。家にも、学校にも自分の居場所を見いだす事はなかった。どこにいても、自分のいるべきではない場所だって、いつもそう思っていた」
ぼくは何もなく無限に広がる、次元の狭間を見渡して力無くつぶやいた。
「その結果がここだったのかも知れない」
あり得ない世界。あり得ない存在が生息する世界。
それは言い換えればこの世にあってはいけない存在の行き着く場所。それが、この『次元の狭間』なのかも知れない。
事実、ぼくの体はどこかおかしくなりかかっていた。
この世界に来るごとにこの世界に順応していく体。
常人なら即座に否定され叩き出されるだけのこの世界に、受け入られ始めている。メネシス同様にこの世界に歓迎され、傷が治ったり不足したエネルギーが供給される。
何よりもこの世界を快適と思い始めている精神…この世界に迷い込んだ直後はいつも気分が良かった。それこそ、ぼくの精神がこの世界を受け入れ始めている証拠ではないか。その快適さが元の世界に戻ってからの恐怖だった。苦痛なら拒否する事ができる。
恐怖なら逃げる事ができる。
安息では逃げるのがためらわれる。
受け入れてしまいそうになる。
真っ当に生きるつもりならはねのけるべきものさえも。
『そうだ、お前がここに来るごとにお前の『座標』は狂い本来いるべき居場所を見失い…本来自分がいた場所を見失っていく。そして、世界に拒絶される』
ぼくはその言葉を聞きながら感じていた。
ぼくは世界に拒絶されたのか。
それとも、『世界を受け入れる事ができなかった』のか。
『オレがお前自身にのみ干渉できたのもお前の座標が希薄になりつつあったからだ…条件はあったがな』
「条件?」
『お前が一人でいる事さ。お前が誰かの視線にさらされている時、誰かがお前を認識している時、その時そのものの座標は強く確立する』
一人でいる事…誰かが認識している時…ネメシスのその言葉が強くぼくの胸に突き刺さる様だった。
『例えるなら、心霊スポットがいい例か…皆が噂を聞きつけて、そこには『霊がいる』と強く思う様になる。そうすると存在が希薄な霊はそう言った人間達の思念を受けて存在が確立されやすくなり、認識されやすくなる。その結果、幽霊がよく目撃される様になるという訳さ』
「逆を言えば、存在が認識されにくいものほど、それがこの世に存在するという事が希薄になるという事かい。その希薄な存在なら、あり得ない世界の存在が干渉する事もできる…」
『そうだ。生き物や物が絶対的にその世界に存在しているという事だけじゃあない。相対的に、相互的に存在を認識し合うのも存在が確立する大きな要素なのさ。
だからこそ、お前達が言う『神隠し』は人が見ている前では起こらない…その存在が確立されているから、他の世界の存在が介入できる余地もなくなる』
ぼくは、今になって人との関わりを避けてきた自分を思い起こした。家庭、学校、友達付き合い…何もかも避けてきた。人に認識されるという事自体を避けてきた、そう言っても差し支えないかも知れない。
『しかし、ほんの数日間でここまで『座標』が狂うとはな…何か心当たりがあるんだろう、リョウト?』
メネシスがぼくの顔をのぞき込む。ぼくは、その態度を意に介している余裕もなかった。
『とりあえず忠告しておく…次元の狭間に意図的に入り込もうとしたり、オレの様に空間を跳び超えたり空間を切り裂くなんて真似もできる様になるのかも知れないが、それはやめておけ』
…空間を…跳び超える…?ぼくはふと、父さんを暴走車から助けようと必至で駆けた時、百メートルほどの距離を一気に跳び超えた時の事を思い出した。
『この世界に来ようとする事は、現実の世界に存在する自分を否定しようとする行為だ。『座標』をすり減らす。後の二つについては論外だ。次元の狭間に来ようとする事の応用で、空間に意図的に干渉しようとする事だ。何度かやれば、世界に拒絶され自分の世界に存在するための座標は確実に狂い、二度と帰れなくなる』
二度と帰れなくなる。その言葉がぼくに重く響いた。あの時は夢中で何も考えていなかったが、父さんを助けるための代償はあまりにも大きなものだった様だ。
『心当たりがあるっていう顔だな…』
メネシスは関心とも驚きとも思えない声でつぶやく。直後、おもむろに背を向けつぶやいた。
『話は終わりだ。自分の世界が好きならせいぜい気をつける事だ…。今なら強く願えば帰れるだろう』
「!?」
ぼくは面食らった。忠告だって?気をつけろだって?
「メネシス…どういう事だい。君はぼくにその事を告げるためだけにぼくを呼んだのか?」
『その通りだ』
メネシスは何の感情も込めずつぶやいた。
「なぜそんな事を?いや、この前ぼくがトゥールに襲われた時もそうだった。なぜ君は、ぼくに関わろうとするんだ?」
場に重い沈黙が訪れた。時間にしておよそ数秒後、メネシスは背中を向けたままで返答する。
『…退屈だったからだ』
「…退…屈…?」
『言葉の通りだ。それ以上でもそれ以下でもない。ただそれだけの理由だ』
驚くぼくを尻目にメネシスは続ける。
『退屈なんだよ。何もする事がない。働く必要がない。食う必要がない。眠る必要がない。かといって何もする事がない。どこかに行ける訳でもない。死ぬ事すらない。オレにとってこの世界はそういう存在なんだ。』
メネシスはぼくに向かって振り返った。
『そこに体よく暇つぶしになる様な奴が現れた。その程度なんだよ。あいつだって同じ動機だろうぜ』
「あい…つ…?」
ぼくはふと脳裏に、父さんに向かって突っ込んできた暴走車のドライバーに襲いかかっていた怪物を思い出した。
『お前達の世界で話題になってるであろう、次元の魔物だよ。名前は『ネル』っていったか…』
「知ってるのかい?」
『ああ、ねじくれた奴だった。挨拶もなくいきなり現れてオレに襲いかかってきた。弱い奴だったから、軽くぶちのめしてやったがね…あいつらしい暇つぶしだ』
「暇つぶしだって…?そんな程度の動機で人の命を奪っているというのかい?」
『だろうよ』
相変わらずメネシスは何の感情も込めずつぶやいた。
『そういう事なんだよ。『ここ』は社会常識だの倫理だのそういうもんを狂わせる。自分以外、何もないんだからな。トゥールの奴は自分自身にしか興味はないみたいだがな。オレ自身、お前がオレ達の仲間になってくれれば退屈しないですむなと思っていたぜ。お前が二度と自分の世界に戻れなくなるのを承知でな…』
一呼吸置いてメネシスは続けた。
『ここは牢獄だ。何もしなくてもいいんじゃない。何をする事も許されない。死ぬ権利すら存在しない』
メネシスの声はどことなく自嘲的だった。『牢獄』。その単語がぼくの胸に大きくのしかかる。ぼくはそんな所を無意識の内に居心地のいい場所と思ってしまったのか。そんな所に永久に棲む事になり、二度と戻れない…それを考えると氷を背中に押し込まれた様に鳥肌が立った。
「…一つ教えてくれ、メネシス。何で君は、ぼくの名前を知っていたんだい?」
『お前の事は、顔を合わせる前から知っていた。座標が狂っているという意味で似たもの同士だったのかな…時々お前の顔や思考がオレに流れてきた。次元の狭間に迷い込む度にオレの所に来たのも、似たもの同士が引き合ったからだろうな…』
メネシスは軽く上を見上げながらつぶやいていた。直後にぼくの方へと振り返る。
『さあ、早く帰れ。自分がいた世界を心の中で強くイメージしろ。そして、なるべく多くの人間が自分を認識する様に努めて生きていくんだ。まだ間に合うだろう…』
メネシスはぼくに背を向けて歩いて行ってしまった。その姿は、恐ろしい異形の怪物とは思えないほどちっぽけでかわいそうなただの人間に見えた。
ぼくは、目を閉じ元いた自分の世界を強く頭の中に思い浮かべる。自分の体が軽くなっていく。
「さよなら、メネシス。もう二度と会わないだろう」
色々な事を考えた。
母さんがぼくに向けてくれた笑顔。
父さんがぼくに向けてくれた思いやり。
クラスのみんながぼくに向けてくれた関心。
ぼくはどこにも自分の居場所がないと思いこんでいた。
一人で思いこんでいたんだ。
少し辺りを見回せばあったものにさえも、
目を向けようとしないで…
気付いた時、ぼくは家の近くの空き地に一人たたずんでいた。既に日は落ちて真っ暗になっていた。ぼくは地面に落ちていた買い物袋を拾い上げると、電気の明かりが灯るぼくの家、いや、『ぼく達の家』へと歩いていった。
すっかり日は暮れていた。時間にすれば、午後七時を過ぎているだろうか。これほど遅れてしまっては父さんも帰ってきているだろう。車庫に父の車が見える。母も怒っているだろう。料理の約束をしていたのに破る事になってしまった。良人の胸中は申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、かけがえのないものを手に入れた気持ちでいっぱいになっていた。良人は勢いよく扉を開ける。
「ただいま!」
良人がリビングを見回すと、電気やテレビが付いていた。飲みかけのお茶もある。しかし、家にいた志乃や帰宅しているであろう浩一の姿は見えない。
「…?」
二人はどこに行ったのだろうか。リビングを通り、キッチンへと向かう。台所には電気がついていなかった。まだ夕食の用意はしていないのだろうか。良人は間に合ったかな、と思いつつも不思議に思った。手探りでキッチンの電気スイッチを探り、スイッチを入れた。途端にキッチンが明るくなる。しかし、キッチンには誰もいない。
その時ふと、テーブルの影に何かがあるのに気がついた。良人は不思議に思って歩いていく。途端に、良人は足取りが重くなった。
「………」
何かの気配がする。このまま前に進めば恐ろしいものを見てしまう。そんな気がしてならなかった。動悸が早まる。足が震えてる。良人の全身の細胞が直感で訴える。
この先に行くな。
この先に行くな。
良人は勇気を振り絞って歩みを進め、その影をしっかりとにらみつけた。
しかし、そこには何もなかった。ただの影だった。しかしその直後、良人は驚愕する。
これは影ではない!影が、黒みを帯びた赤だった。血!
直後、ガリッ、という何かを引っ掻く様な耳に心地悪い音が台所の奥の部屋から響いてくる。
よく見れば、血は血痕となって奥の部屋へと続いていた。良人はその血痕を凝視しながら奥の部屋へと歩いていく。
再び、良人の動悸が早まる。
「!」
そこで良人が見たのは、頭から血を流しながら横たわる母、志乃の姿だった。
「母さん!」
直後に再び何かを引っ掻く様な不快な音が響き渡った。
何かを引きずる音が聞こえる。
暗闇に白い二つの光が見える。
「父…さん…?」
暗闇から出てきたのは、父浩一の首筋に噛み付く異形の怪物だった。あの姿は、以前の暴走車のドライバーに襲いかかっていた次元の魔物。メネシスが『ネル』と呼んでいた『神隠し事件』の犯人だった。
「うわあああぁあぁあああっっっっ!」
良人は手に持っていた買い物袋を床へと落とした。ボトルが床を転がる音が響く。卵は不吉にも嫌な音を立てて割れた。次元の魔物、ネルは良人をその目に捉えると、口にくわえていた浩一を無造作に投げ捨て、良人へと飛びかかっていた。その禍々しい牙をむき出しにして。
次元の魔物。『神隠し事件』の犯人。どうやって次元の魔物である彼が自分達の世界に現れて人を襲うのか、それはわからない。ただ、言える事はその怪物が今まで何人もの罪のない人間に牙をむき、命を奪っていたという事実。その牙が両親へと向けられ、今まさに自分ののど笛を食いちぎらんと自分に牙をむいている事。その怪物の名前はネルといった。そして、その獲物は良人だった。
「ああ…っ、あっ…」
良人が力無く声を上げる。倒れた胸の上には鋭い爪を持つネルの前脚がズッシリと重く押しつけられていた。
『グッ、ガッ、ガアァッ!』
獣そのものの唸り声を上げ、唾液の滴る牙を良人の眼前でチラつかせる。牙は既に、両親の血で濡れていた。
良人は今になってやっと悟った。ネルは、ずっと自分を狙っていたのだと。度々感じていた視線はメネシスのものではなくこのネルのものだったのだ。あの時、父を助けた暴走車の事件現場に居合わせた時からネルは次の標的を自分へと定めていたのだ。そのさなか、メネシスに引きずり込まれる形で次元の狭間へと流れた。手出しのできなかったネルは、しびれを切らして爪牙の矛先を良人の両親へと向けたのだ。確実な死の予感を前にしながら何もできない。良人は震えた。トゥールの時の様なメネシスの助けは期待できない。
…どうあがいても、絶望だった。
良人は少しずつ横目で志乃と浩一の方を見た。血を流し倒れている。死んでいるのだろうか。
「うっ…!」
「!」
志乃が一瞬うめき声を上げた。浩一の体もわずかに震えた様だった。まだ、生きている!
「うわああああっ!」
突然、ネルは良人の左肩にかぶりついた。悲鳴を上げる良人。ネルは自分から目を離した事が許せない様だった。
『ナニよそ見してる…今の立場がわかってんのか?』
ネルは低くくぐもった声で良人につぶやいた。
「な、なんで…ぼくを?両親を?」
『派手に事故を起こそうと思ってたのに邪魔しやがって…ウザイ餓鬼は死ね』
肩口にかじりついた牙に力が入る。
「ぐあああぁぁああっっっ!」
血が噴き出すとともに鈍い音が響く。鎖骨が折れた様だ。良人の目は痛みと恐怖で引きつり、息は荒く口は金魚の様にパクパクとしていた。ネルはそれを見て愉快そうに目を歪めた。
『餓鬼がァ!』
ネルの前脚が良人のみぞおちに落とされる。
「ごぶっ!」
胃液が逆流し、良人は反吐を吐いた。その光景を見て、ネルは再び愉悦に顔を歪めた。これだからたまらない。子供は少し痛めつけてやればすぐに泣きわめく。それは自分にとってこの上ない快感だった。ネルは人を狩る事を自分の娯楽とした。
ネルはふと思い出した。次元の狭間にいた頃の事を。そこは、気楽な場所だった。自分に命令したり干渉したり、群れてつるむ目障りな奴らもいなかった。何もしなくてすんだ。だが、何もしなくていい代わりに何もする事がなかった。
あの忌々しい人間どもの社会を滅茶苦茶にしたい、ネルは常にそう考えていた。そして、ついに成功した。ごく限定的だが、ほんの一時的に人間達の世界に現れ、人を殺す事ができる様になった。それまで退屈だった自分の生活は楽しいものになった。殺した人間は命のない死体、物と同じだ。自分のテリトリーに持ち帰るのはそれほど難しい事ではなかった。自分が殺した人間は突如行方不明になる怪事件と騒がれ人間達の恐怖を煽るだろう。この上なく心が晴れる。
だが頭の中を覗き見るうっとうしい奴が現れた。自分の殺しを覗き見、思考に流れ込んでくる人間が。どうやら自分は、この人間を人間の世界に現れる目印としていた様だが、ハッキリ言ってウザイ。俺の正体を少しでも感じ取れる奴がいてはならないのだ。だからこいつには逝ってもらう。こいつを殺しても他の奴がどこかに現れるだろう。そして憎たらしい人間どもを殺して殺して殺しまくってやる。俺を虚仮にした人間どもは全部死ねばいいんだ。世の中は荒れに荒れるぜ。
「………!」
良人は激痛の中、ネルを間近にして彼の思考を感じた。良人の心に大きな驚愕が広がる。
何という自己中心的で救いようのない思想なのだろうか。
『似たもの同士が引き合った』
メネシスはそう言っていた。それと同じ事が自分とネルの間にもあったのだ。こんな奴と少しでも似た思いを抱いたなんて。自分が恐ろしくなった。もし両親やみんなを憎み、疎み続けていたらこんな奴になったのか…?そんな自分の可能性としての存在が目の前の醜悪なネルだと思うと自分が恐ろしくなった。
そしてもう一つ。ネルの殺害現場を奴の視点で感じたのは、ネルと同じ様な感情を抱き、意識がわずかに同調したからなのだ。ネルの心は人間に対する憎しみ、恨み、蔑み…あらゆる呪いとも言える感情で満ちていた。自分がそんな思いを抱いてしまったから、ネルは自分を通して自分達の世界に現れる事ができる様になってしまった。ぼくは何て事をしてしまったんだ。
だが、全てが遅すぎた…。
今自分の上には人の命を何とも思わない醜悪な怪物がぼくの命も奪わんと牙をむいている。そして、ぼくを殺した後、父さんと母さんの命も喜々として奪うだろう。
許せない。
だが、ぼくにはなすすべがなかった。できるのは氷の様に冷たい自分の死を見つめる事だけだった。生きたまま蛇に呑まれる蛙はまさにこんな心境なのだろうと肌で感じていた。
ネルは、ぼくの首筋めがけてかぶりついてきた。ぼくは両手で必至にネルの頭を押し返そうとした。
しかし、無駄な抵抗だった。ネルの首を絞めようとしても、全く効果がない。大の大人がどうにもならないのに、こんなちっぽけな小学生の子供に何ができるだろうか。ぼくは死を覚悟した。前にトゥールに襲われた時も、こんな風に感じたんだった。
頭の中に色々な事が思い出された。
これが死ぬ瞬間に見るという走馬燈なのだろうか。
その時、ふと思い出した。メネシスの言葉を。
『オレの様に空間を跳び超えたり空間を切り裂くなんて真似もできる様になるのかも知れないが…』
…ああ、確かにメネシスの様な事ができれば、こいつを倒す事ができるのかも知れない…。
ぼくはハッと我に返った。もし、メネシスがトゥールにやった様に『空間を切り裂く』なんて事ができれば…!
「(切れろ切れろ!切れろ切れろ!)」
ぼくはネルの首筋をつかんだ手に力を込め必死に念じた。だが何も起こらない。
「切れろ切れろ切れろ切れろ!切れろぉっ!」
ぼくはいつの間にか必死で声に出して叫んでいた。だがやはり、何も起こらない。
『何の真似だ…ええ!?』
ネルはあざ笑いながら牙に力を入れる。
『そら、もうちょっとでお前の頸動脈は千切れるぜ!』
「あああぁぁぁあああっっっ!!!」
失神しそうな痛みがぼくの体を電流の様に駆け巡る。
もう助からない。
死の覚悟なんてもうとっくに済ませたはずなのに、
痛みに再び死の恐怖を呼び起こされる。
痛みは恐怖に、そして諦めへと変わっていく。
その直後に思ったのは、すぐ側で倒れている父さんと母さんの事だった。
ぼくはもう助からない、死んでも構わない。
二度とこの世界に戻ってこれなくなっても構わない。
‐神様、どうか二人を助けて下さい。
次の瞬間、赤い大量の血液が良人の視界を覆った。
良人の中で決定的な何かが切れた。体が硬直して、全ての回路が焼き切れた様だった。
良人が消えゆく意識の中で見たのは、弾けたザクロの様にザックリと裂けた、
…ネルの頭部だった。
力を失ったネルの体がゆっくりと良人へと覆い被さる。
その直後、ネルと良人の姿は元から存在しなかったかの様に、跡形もなく消え去っていた。
ただ、そこに残ったのは血痕だけだった…。
従来の怪事件、『神隠し事件』と同じ様に。
悲鳴と絶叫を聞きつけて駆けつけた近所の住民が間宅に駆けつけた。血を流して意識を失っていた浩一と志乃を見て、直ちに警察と病院へと通報が行われた。
救急車に運ばれる浩一と志乃。出血は多いが命に別状はないらしい。現場検証を始める警官達。いずかへ逃げたであろう犯人を捜す警官。それに平行して、姿を消した男の子も捜索された。しかし、警察の懸命な捜査にも関わらず犯人と男の子は見つからなかった。この事件も怪事件『神隠し事件』と同一とされた。
この事件以降、江須市を騒がせていた『神隠し事件』は途絶えた。無数の行方不明者を残して。
そしてその最後の行方不明者の名前は、間良人といった。
そして、『神隠し事件』は終わりを告げた。
約一ヶ月後…冬はすっかり深まり、クリスマスシーズンを迎えていた。きらびやかな電飾が商店や家を彩り、人々に活気を与える。子供達はここぞとばかりに親にプレゼントをねだる。どこの家庭も似た様なものだった。
その商店街から離れた郊外の住宅だった。一人の主婦が電柱へと貼り紙をしていた。そこに、一人の背の高い男が通りかかる。外国製のものと思われる緑のコートを着込み、汚れたブーツを履いていた。服装は所々が傷み汚れている。身なりがいいとは言い難い男だった。
主婦はそんな男を見て不審に思ったが、何か気になる事があったのか遠目で顔をのぞき見る。
「…何か?」
男は主婦に問いかける。主婦は面食らいながらも、恐る恐る男に問いかける。
「あの…男の子を見ませんでしたか?小学五年生で、そう、この写真の子なんですけど…」
男は主婦が貼っていた貼り紙を手渡された。小学生の男の子の写真があり、『この子を捜しています』と書かれている。男はしばらく眺めると、無言で静かに首を横に振る。主婦はキョトンとして男に問いかけた。
「あの…あなた…お名前は…」
言い終わらない内に家の中から男が出てきた。
「志乃、今日はその辺にしよう。雪が降るぞ」
「ええ、今から夕食にしましょう…」
その男は主婦の夫の様だった。夫に呼ばれ、主婦は家の中へと入っていく。一人取り残される男。
「…リョウトです…」
男は小さくつぶやいた。男の体が震えている。
「僕の名前は間良人です…」
男の頬から滴が伝い、貼り紙の男の子の写真へとこぼれ落ちる。滴はインクをにじませ同じ名前の男の子を濁す。
男は涙を袖で拭うと歩き出し始めた。
『よかったじゃないか…ようやく会えて…』
「そうだな」
男は誰と話しているのか、つぶやいていた。
『ここまで来るのに十年以上かかったけどな…』
男は歩みを進める。空に粉雪がぱらつきだした。
『そろそろそこにいられるのも限界みたいだ』
歩く男の周囲が次第に暗くなっていった。
『次は暖かい所に行けるといいな…』
「ああ…」
やがて男は音もなく、消え入る様に姿を消した。
少年に訪れた奇妙な体験は、本当の神隠しとなって彼を遠い彼方へ連れ去った。
その後、彼の姿を見た者はいない…。
(カミカクシ 完)